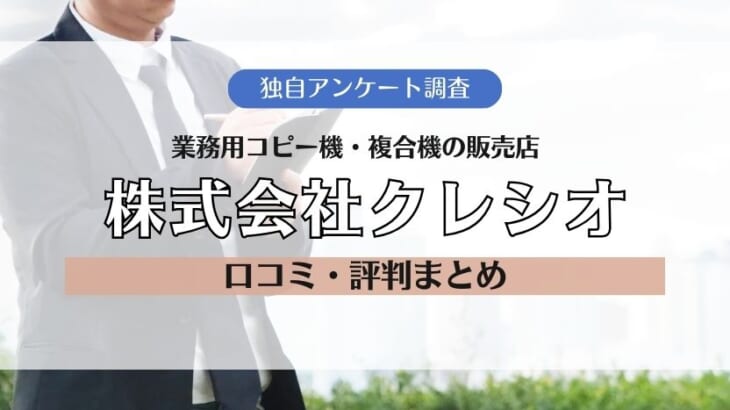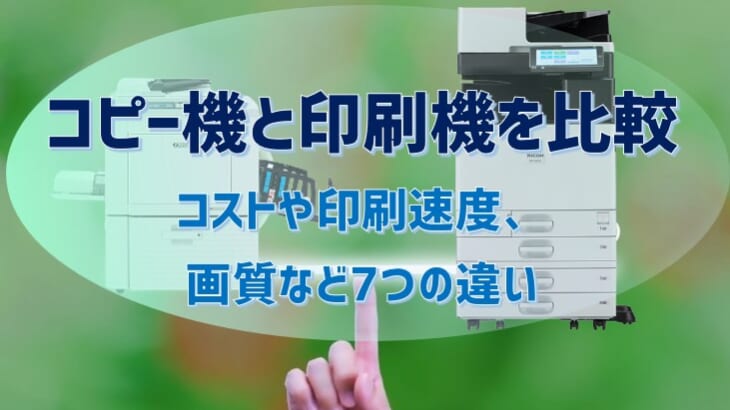新品と比較して安いなどの理由で、中古複合機の導入を検討するケースもあると思います。
しかし、中古複合機は本体価格が安い代わりに、大きなデメリットがあります。ズバリ!中古複合機のデメリットは、保守です。
その点を知っておかないと、購入後に思わぬコストが掛かってしまい、中古購入のメリットがなくなってしまいます。
中古複合機のデメリットをしっかりと把握したうえで、複合機・コピー機の機種を選定しましょう。
>>>「中古コピー機・複合機のおすすめランキング」記事はこちら
私は、大手事務機メーカーのコピー機を製造する工場で、生産技術職として8年間ほど従事していた経験があり、紙を搬送するメカニズムや画像を形成するメカニズムについて熟知しているつもりです。そんな私から、複合機・コピー機についての情報をお伝えさせて頂きます。
中古複合機のデメリットは保守費用が高くなること
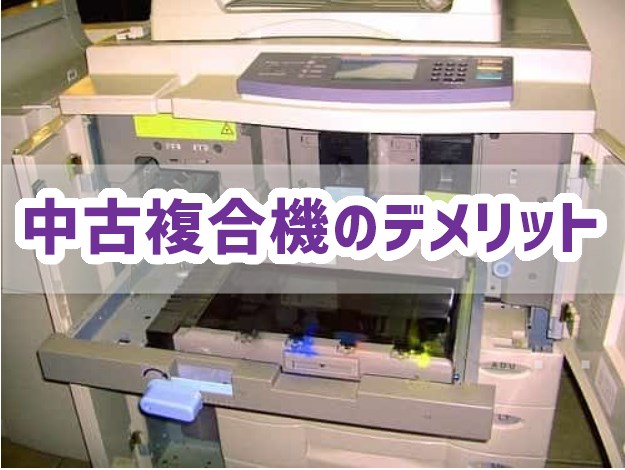
複合機・コピー機を購入する際は、クリーニングやメンテナンスを行ってもらうために、メーカーや販売店と保守契約を結びます。
現在の保守契約は、カウンター式と呼ばれる1枚印刷するたびに費用が発生するタイプが主流です。>>複合機のカウンター料金とは?
使用中にトナー切れや故障が生じることもありますが、その都度料金が発生するのではなく、毎月カウンター料金を支払うことで、トナーの支給やメンテナンス、修理対応を保証してもらう方法です。
中古品の場合は、保守契約が必須ではなく任意となります。
しかし、メンテナンスや修理に掛かる負担を考えると、保守契約を結ばれるケースが大半でしょう。
中古品は新品と比べてメンテナンス費用が大きくなるため、カウンター料金が高く設定されることが多く、また、場合によってはメーカーや販売業者が対応できず、保守契約を結べない可能性があります。
 オペレーター 杏奈
オペレーター 杏奈
【中古複合機のデメリット】保守費用が高い理由
中古品は故障リスクが大きく、メンテナンス費用が新品よりも掛かってしまいます。
そのこと自体はイメージできると思いますが、具体的に新品と比べてどのようなデメリットがあるのか?を技術的な観点からお伝えします。
部品の耐久性が低く交換頻度や修理対応が増える
中古の複合機・コピー機は、以前の所有者の使い方によって、部品の消耗度が異なり、思わぬ部分でダメージを抱えている場合があります。
もちろん、中古品で売られている製品でも、消耗品として設定されている部品を交換したうえで受け取ることができるでしょう。しかし、それ以外の部品については、どのような状態なのか?が分からず、思ったより早いタイミングで故障や劣化による不具合が発生する可能性があります。
交換できる部品の生産量が少なくなる
複合機・コピー機は数年単位のサイクルで新製品が開発されており、中古で使用されている部品は、生産量が少なくなり、交換部品の単価が上がる場合もあります。
さらに、部品の生産自体が終了してしまうと、交換対応ができず、修理自体が不可能になることもあります。
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
中古の複合機・コピー機で起きやすい不具合
複合機・コピー機は、主に以下の工程を経て、画像や文字を出力します。
- 給紙
- 帯電&露光
- 現像&転写
- 定着
- 排紙
各工程の間には、用紙を受け渡し合う「搬送」の工程もあるので、それも含めた各工程を見ていきます。
給紙
給紙トレイにセットされた紙を搬送するために、用紙の束から1枚だけピックアップして本体へ搬送する工程です。用紙のピックアップや分離がうまくできていないと、この時点で紙詰まりを起こします。
給紙するためのローラーなどは消耗品なので、単品で交換パーツとして設定されていますが、その他の構成部品に不具合が生じた場合は、ユニットごと交換となる場合もあります。
機能的に難しい部分なので、使用回数が増えることでの故障や劣化が多く、また、故障だけでなく部品の位置調整なども細かい部分のため、調整のズレによる不具合も起こります。
搬送
ピックアップされた紙は、画像形成するエリアを経て、排紙トレイまで搬送されます。紙詰まりは、この搬送ルートのどれかの部品に不具合が生じて起こることが多いです。
搬送部には、場所によってプラスチック部品と板金部品が使われていますが、部品自体の消耗よりは、部品と部品の位置にズレが生じて、不具合を起こす場合が多いでしょう。
また、印刷枚数が多いほど部品と用紙の摩擦が発生しているので、用紙にキズを付くなどの不具合が生じる場合もあります。
帯電&露光
画像や文字のデータを用紙へ転写するための前準備を行う工程です。
感光体ドラムと呼ばれる大きなローラーの上に静電気を帯びさせて、画像や文字の場所に光を当てることで、ドラム上に画像を形成します。
この工程は光学部品が使われていたりプロセス的な調整が多く、不具合が生じた時に、少し手直しを行うことや部品単品を交換して修正することが難しい場所です。
そのため、帯電させる帯電ユニットや露光を行うスキャナユニット、画像を形成されるドラムユニットなど、ユニット単位で交換パーツ設定されていることが多く、交換にコストが掛かってしまいます。
現像&転写
用紙に画像や文字を転写するプロセスです。光を当てた部分がトナーを吸着し、画像や文字を用紙に転写します。
トナーボトルから供給されたトナーを均一に用紙へ付着させるために「現像器」と呼ばれるユニットを用います。ドラムに乗せたトナーをそのまま用紙へ転写したり、ベルトを介して用紙へ転写させます。
この工程を構成するユニットは、トナーとの関係や部品の位置調整、圧力調整など、かなりシビアな規格で成り立っています。画像の色が抜けたり、色がズレる場合は、この工程のどこかに不具合が生じています。
画像の品質に影響を与える不具合は、この工程で起きることが多いでしょう。
定着
用紙に乗せたトナーが剥がれないように、ローラーなどに熱と圧力をかけて定着させます。
高温になり、明らかに部品へのダメージが大きい工程なので、はじめから強度や耐久性を持った材料・形状などで構成されています。
そのため、使用しているうちにちょっとしたズレで不具合が起きることはあまりないと思います。あるとすれば、加熱や圧力など、大きな不具合でしょう。
圧力が不足していたり均一でなかったりすると、ぼやけた画像やムラのある画像に仕上がります。
排紙
定着直後の用紙は高温で静電気を帯びているため、用紙を冷却しながら除電して、排紙トレイへ送り出されます。また、両面印刷などの際に、用紙を反転させる機構を持つのも排紙の工程です。
熱が加わることで高温になり、たわみやすくなった用紙を搬送することや、排出方向に搬送された用紙を反転させて再び搬送経路に戻すことで、紙が真っ直ぐ進まずに斜行して、紙詰まりを起こすことがあります。
ここは部品単体の消耗よりも、どちらかと言えば初期不良が多い場所です。
【まとめ】中古複合機・コピー機のデメリット
複合機・コピー機がどのように動作しているか?を考えたことがないかもしれませんが、給紙から排紙まで様々な工程を経て印刷が完了します。
各工程には、たくさんの技術が詰まっており、使用頻度が上がることで、部品のズレや劣化が進みます。
トラブルやストレスを抱えることなくコピー・印刷を行うためには、製品の安さだけでなく、購入後に起きる可能性が高い不具合など、デメリットも頭に入れて検討しましょう。
- 中古品は本体価格こそ安いが保守費用は大きくなる
- 部品の生産が終了すると修理が受けられなくなる可能性もある
- 部品ではなくユニット単位で交換する部分はコストが掛かる
- 工程によって使用頻度が影響するもの、初期不良が多い部分がある
* * *