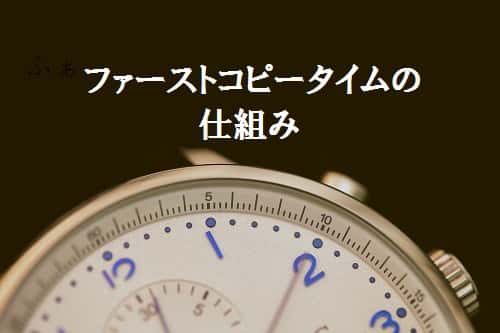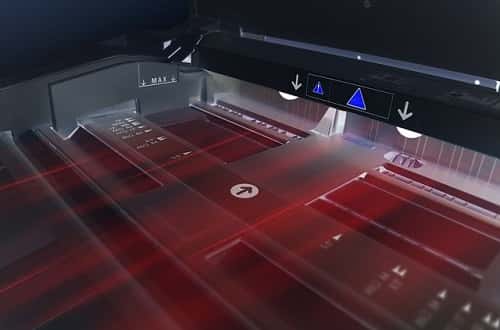【全メーカー対応】複合機のお見積り
30社の複合機販売店を独自調査したコピー機Gメンが、安さと対応力に優れた販売店を2~3社ご紹介します。
* * *
複合機・コピー機のウォームアップタイムの仕組み

コピー機・複合機のウォームアップタイムとは主電源スイッチを入れてからコピー動作が開始できるようになるまでの時間です。
また、コピー機・複合機は電源を入れている間、かなりの電力を消費するため、一定時間の操作が行われないと自動的に電力消費を抑えるモードが設けられています。メーカーや製品によっては、主電源を入れてからだけでなく、この省エネモードからの復帰時間もウォームアップタイムとして公表しています。
ウォームアップタイムが短いコピー機・複合機メーカー
- 第1位 シャープ
- 第2位 京セラ
- 第3位 コニカミノルタ
※30~35枚機で比較した場合。
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
 オペレーター 杏奈
オペレーター 杏奈
大手事務機メーカーのコピー機部門で、生産技術職として約8年勤務していました。本体の生産ライン立ち上げなど生産技術系の仕事で様々な本体の問題を検討してきたので、基本的な幅広い知識を持っています。
ウォームアップタイムの大きなウェイトを占める「定着部」は、製品が新しくなるたびに変化をしている印象がありました。技術的にも大きな違いがあることを知って頂きたく思います。
今回はウォームアップタイムが上下する要素は何か?を中心にお伝えしていきます。
複合機・コピー機のウォームアップタイムは定着部がカギ!

出典:Amazon
ウォームアップタイムは、定着部がどれだけ早く準備できるか?が関係しています。
コピー機・複合機は、インクジェットプリンターのようにインクを使用するのではなく、粒状の樹脂であるトナーを用紙に乗せて、熱と圧力を加えることで定着させる印刷方法です。定着を行う部分は樹脂を溶かすために、かなりの高温にしなければならず、必要な温度になるまでの時間がウォームアップタイムに大きな影響を与えます。
定着を行うのは、熱と圧力を同時にかける構成を持つ「定着ユニット」で、印刷物を排出する直前に『印刷工程の最後の砦』として待ち構えています。
まずは印刷の仕組みとともに、定着ユニットの構成を見ていきましょう。
印刷の仕組み
印刷の工程は、大きく分けて以下の通りです。
コピー機・複合機では、静電気の力で画像や文字が描かれる場所にだけトナーを運び出しますが、それだけでは触れるとすぐに剥がれてしまいます。
そのため、⑤の工程でトナーが溶ける温度まで加熱し、圧力を加えて用紙に密着させ、定着しています。
- 帯電:ドラム表面全体を均一に帯電させる
- 露光: 出力された画像や文字の通りに光を当て、ドラム表面内に電荷の差を発生させる
- 現像: 電荷の差によって、光が当たった部分にのみトナーが吸い寄せられドラムに像が描かれる
- 転写:トナーによって描かれた像を紙へ直接転写する、または転写ベルトに1度移してから紙へ転写する
- 定着: 紙に乗せられたトナーに熱と圧力を加えて定着させる
定着ユニットの仕組み
⑤の定着工程では、トナーを加熱しながら押し付けることで用紙へ融着させます。
多くの製品で採用されている基本的な構成は、定着ローラーもしくは定着ベルトを加熱し、対向する位置に加圧ローラーもしくは加圧ベルトを設置しています。常に最適な温度で加熱しなければならず、用紙が通過することで熱が奪われてしまうため、効率を落とさないまま定着するように常に温度制御が働き、大きな電力を消費します。
定着ユニットの構成でウォームアップタイムは大きく変化し、メーカーや製品によってウォームアップタイムを改善するために様々な工夫がされています。
続いて、定着ユニットの構成として代表的なものを以下に紹介します。
【全メーカー対応】複合機のお見積り
30社の複合機販売店を独自調査したコピー機Gメンが、安さと対応力に優れた販売店を2~3社ご紹介します。
* * *
定着ローラーとヒーター加熱
これまで多く採用されていた構成は、定着ローラーと加圧ローラーの2対によるもので、定着ローラーの内側にヒーターを設置して加熱する方式でした。
定着ローラーには、接触面積を確保するため、ゴムなど弾性体の層が設けられており、ある程度の厚みが必要です。そのため、熱伝導率が悪くなってしまい、ウォームアップタイムが長くなっていました。
ウォームアップタイムが長いことは紛れもないデメリットなので、それを解消しようと、加熱部の定着ローラーを薄肉化し、対向する加圧側をスポンジローラーにしたり、または加熱部をローラーではなくフィルムにするなど、接触面積を増やして熱伝導率を高めた様々な方式が増えています。
定着ベルトとIH加熱
カラーの場合は、トナーを重ね合わせているため、モノクロよりも大きな熱量が必要です。カラー機の普及と高速・高画質化に伴い、熱効率を高くして接触面積も大きくできる方式が増えています。
まずは、IH(電磁誘導加熱)方式による加熱です。
従来のヒーター加熱ではヒーターが発熱して定着ローラーなどへ熱を伝達しますが、それに対し、IH加熱では磁力の力で定着ローラー自体を発熱させます。それにより熱伝達の損失が少なく、短い時間で高い熱量を発生させることができます。
IH加熱を用いることで、ウォームアップタイムが従来機の半分以上も短縮可能になっています。構成としては「IHコイル」と言う加熱源を、定着ローラーの内側に設けたタイプと外側に設けたタイプがあります。
また、定着ローラーのように円筒の部品ではなく、金属の薄いベルト状にした方式も増えています。
これにより熱伝導率を高くし、昇温するまでの時間を短くすることができます。加熱自体もベルト全体を温めるのではなく、用紙に接する部分もしくは近い範囲を直前で加熱するなど、昇温時間を早めると同時に電力の消費を抑える工夫がなされています。
【全メーカー対応】複合機のお見積り
30社の複合機販売店を独自調査したコピー機Gメンが、安さと対応力に優れた販売店を2~3社ご紹介します。
* * *
電源を落とさずにコピー機を休ませる省電力モード
コピー機・複合機の主電源スイッチを切れば、全ての通電を止めるので、消費電力はほとんど掛からなくなりますが、またスイッチを入れ直して、再びコピーをしようとすると、数10秒のウォームアップタイムを必要とします。
そこで、ほとんどの製品には一定時間の操作が行われないと、自動的に電力の消費を抑えるモードが設けられています。設定時間をユーザーで変更できるようなモードもあり、使用していない時は電力消費を抑え、使用したい時にできるだけ早く、コピー動作を再開できる工夫がされています。
各モードの呼び方や細かい内容は、メーカー・機種などによって違いますが、一般的には以下の3つのモードがあります。
- 節電モード
- 低電力モード
- スリープモード
それぞれの特徴を1つずつチェックしてみましょう。
節電モード
このモードは、メーカーによって呼び方が違いますが、本体の操作部に配置されている「節電ボタン」を押すと、定着ユニットの温度を下げる制御が入り、強制的に消費電力を抑えるモードに切り替わります。
定着ユニットに通電自体はされているので、ウォームアップタイムが一番早い省電力モードです。
印刷を行う時間の間隔が大きく空くわけではないものの、なるべく消費電力を抑えて使用したい場合などに有効です。
低電力モード
一定時間、操作が行われない時に自動で定着ユニットへの通電を止め、電力の消費を抑えるモードで、節電モードとの大きな違いは「定着ユニットの通電を維持しているか?止めているか?」です。
ただし、メーカーによっては節電モードと同じ扱いになっています。
コピーボタンや節電ボタンなどを押せば復帰が可能ですが、節電モードよりも長いウォームアップタイムを要します。
どのくらい経過時間で低電力モードへ切り替えるか?を、ユーザーが設定することもできます。
スリープモード
低電力モードに切り替わってから、さらに一定時間の操作が行われないと、スリープモードに入ります。また、本体操作部の電源ボタンを押すと強制的にスリープモードにすることもできます。
スリープモードでは定着ユニットだけでなく本体のほとんどの場所への通電を止めるため、消費電力は最も抑えられます。
なお、制御系や基盤などへの通電はそのままなので、PCやFAXからの受信は可能です。
印刷頻度が高くなく、時間が空いてしまうような場合は、スリープモードに設定すると良いでしょう。
まとめ
- ウォームアップタイムとは電源を入れてからコピー可能になるまでの時間
- トナーの定着に必要な温度まで昇温させるため、多くの時間を要する
- 定着ユニットに使用する部品や加熱源が工夫され、昇温時間は短縮されている
- 印刷頻度によって省電力モードを使い分けられる
- 省電力モードはウォームアップタイムの短縮だけではなく省エネの観点でもオススメ
* * *