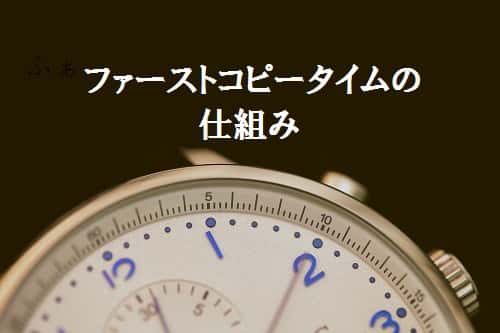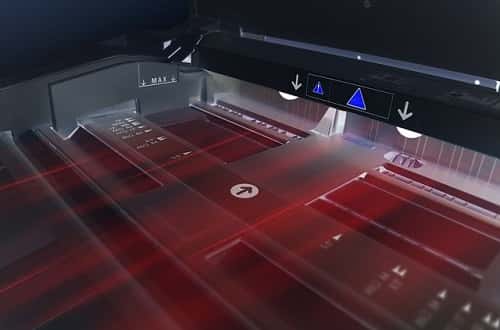【全メーカー対応】複合機のお見積り
30社の複合機販売店を独自調査したコピー機Gメンが、安さと対応力に優れた販売店を2~3社ご紹介します。
* * *
複合機・コピー機の構造~印刷の仕組みと故障の原因~
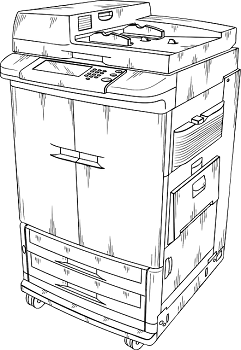
コピー機・複合機の不具合やエラーが増えて悩んでいませんか?
「中古で買って保守契約を結んでいないから業者を呼ぶとお金が掛かるな…」「そもそも業者を呼ぶほどのことなのだろうか?」などと思いながら使い続けている方もいるでしょう。
故障のリスクを増やさないために、印刷品質を保ったまま長く使用していくために、コピー機・複合機について理解を深めることは大切です。
コピー機の内部は、実際どのように動いていて、どの部分でどのような不具合が発生しているのか?を把握することはムダな出費を抑えることに繋がります!
私は大手事務機メーカーのコピー機を製造する工場で、生産技術職として8年間ほど働いていました。
主に生産ラインの立ち上げなどを行っており、生産中に発生する本体の不具合対応やユーザー先で不具合が生じて返品された本体の確認など、毎日のように製品をバラシて検討していました。そのため、コピー機・複合機の内部構造や印刷の仕組みについては熟知しているつもりです。
今回は、コピー機・複合機で用紙をセットして印刷されたものが出てくるまで、どのような工程を経ているのか?を中心に、各工程で起こり得る不具合や原因などを紹介いたします。
印刷の仕組みの理解と不具合の対処に是非お役立てください!
コピー機・複合機の構造と仕組みを理解しよう!

コピー機・複合機の不具合は、多くが紙詰まりと印刷不良です。
程度によってはメンテナンス業者に修理してもらう必要がありますが、そうなってしまうと一時的に使用できなくなり、場合によっては修理のために本体を預けることになります。
不具合を未然に防ぐために、使用上で気を付けるべき点は、どのようなことでしょうか?
【全メーカー対応】複合機のお見積り
30社の複合機販売店を独自調査したコピー機Gメンが、安さと対応力に優れた販売店を2~3社ご紹介します。
* * *
用紙に画像や文字が印刷されて排出されるまで
印刷技術は大きく分けると「電子写真方式」と「インクジェット方式」の2つの方式があります。
「電子写真方式」は、静電気のチカラでトナーを紙に転写し定着させます。一方「インクジェット方式」は、紙に直接インクを吹き付けます。
オフィスやコンビニなどに置かれている、いわゆるコピー機と呼ばれるものは「電子写真方式」を用いており、高速かつ高画質な印刷ができます。
それでは、用紙をセットしてから→印刷→排出されるまでの、一連の流れを説明します。
給紙
本体下部の給紙トレイにセットした紙の束から、1枚だけピックアップして本体へ送り出す工程です。
多くの場合では、回転させたゴムローラーを、給紙するタイミングで紙に接触させて、ピックアップ動作を行います。ピックアップされた紙は、給紙ローラーと対の位置にある分離パッドや分離ローラーなどの摩擦によって「送り出す1枚」と「他の紙の束」に分離され、搬送されていきます。
高級機になると、穴の開いたベルトコンベアのようなものを用いて、空気を吸引することで紙をピックアップし搬送させる給紙方法もあります。この場合は、紙の束にエアを吹き付けて捌くことで、1枚に分離しています。
不具合と原因
給紙の工程で、最も多い不具合は、ローラーなどの摩耗による給紙不良です。
給紙ローラーが摩耗してくると、摩擦力が低下して、紙をピックアップできずに紙詰まりのエラーが起こります。また、分離パッドや分離ローラーの摩擦力や圧力が弱くなると、紙を1枚に分離できず、複数の紙を搬送してしまう『重送』と言われるエラーが起こります。
注意点
給紙の段階で紙詰まりが起きた場合、対応は慎重に行いましょう。
なぜなら、紙が詰まっている部分は給紙トレイと次の搬送路への受け渡し部分に跨っていることが多く、無理に給紙トレイを引き抜こうとすると他の部分へダメージを与えてしまう可能性があるからです。
他の扉を開けてアクセスできないか?など、状況をしっかりと確認しましょう。
また、この工程での不具合は、使用している用紙に原因がある場合も多いです。
紙粉などが多く、著しく摩擦力が低下していると、給紙が機能しなくなってしまうので、用紙は出来るだけ未使用のものを使いましょう。
それ以外では、ほとんどが部品耐久性の低下によるものなので、部品交換の対応になることが多いでしょう。
給紙トレイの開け閉めを乱暴にすると、部品の位置ズレや破損を引き起こすことがあります。僅かな力でも開閉できる複合機が多いので、静かに(丁寧に)扱いましょう。
搬送
ピックアップされた紙を印刷する場所まで運ぶ工程です。
画像や文字を書き出すタイミングと紙の位置を合わせるため、搬送するタイミングを緻密に制御しています。紙の通り道に幾つもセンサーが付いており、通過を検知し、紙が正しいタイミングでやって来たか?滞留せずに通過できたか?を常に確認しています。
不具合と原因
よくある不具合としては搬送中の紙詰まりです。
給紙してから搬送エリアへ、搬送エリアから印刷エリアへと、用紙の受け渡しを続けているので、搬送経路上の部品が変形していると、紙が引っ掛かり紙詰まりになる可能性が高まります。
また、実際に紙が詰まっていなくても、紙の搬送タイミングが早かったり遅かったりすると、紙詰まりエラーとして検知します。同様に、搬送タイミングを検知しているセンサー部分の部品に不具合があると、正常に紙を搬送できていても、紙詰まり検知エラーとなる場合があります。
注意点
本体の内部にあるため、紙詰まりが起きた際に紙を引きちぎってしまうと、他部へダメージを与えてしまうことがあります。操作パネルに表示されている正しい手順で処理してください。
また、紙の角に折れがあると、搬送の受け渡しがうまくいかず、紙詰まりを起こす場合もあります。給紙ではスリ抜けても、ここで詰まってしまうので、用紙のセット時に折れやヨレなどをしっかり確認しましょう。
用紙の搬送経路上に幾つもあるセンサーフラグは、搬送タイミングを検知する大事な役割を果たしています。破損や位置ズレが起きないように、取り扱いには気を付けて下さい。
【全メーカー対応】複合機のお見積り
30社の複合機販売店を独自調査したコピー機Gメンが、安さと対応力に優れた販売店を2~3社ご紹介します。
* * *
印刷
PCから出力や本体で直接読み込まれた画像・文字などはデジタル信号に置き換えられます。
その信号をもとに、描かれた部分のみ静電気のチカラでトナーを引きつけ、用紙へ転写した後、定着することで印刷されます。
一連の流れを細かく見ていきましょう。
帯電&露光
印刷する画像や文字の通りに、用紙へトナーを乗せるための前準備工程です。
トナーの運び屋のような役割をする『感光体ドラム』を用います。感光体ドラムの表面全体に静電気を帯びさせ(帯電)、その上から画像や文字の通りにレーザー光を当てる(露光)ことで、画像部分と余白部分で帯電状態の差を作ります。
現像
感光体ドラム上にトナーを付着させて画像や文字を描く工程です。
感光体ドラムの回転と同期して、マグネットの入った金属ローラーが静電気を帯びたトナーを抱えて回転しています。同じ電荷同士で反発し合う性質を利用して、画像部分のみトナーが付着し、感光体ドラムに像を描きます。
転写
現像した画像や文字を用紙へ転写する工程です。
感光体ドラムから直接、紙へ転写する方式と、転写ベルトと呼ばれるものに一度乗せてから紙へ転写する方式があります。
モノクロは直接転写が多いですが、カラーは紙の搬送タイミングと各色の転写タイミングのズレが生じやすいため、ベルトに全色分を転写し、像を完成させてから紙へ転写させる二次転写方式がほとんどです。
定着
トナーが乗った状態の紙に、画像や文字を定着させる工程です。
ヒーターで熱を加え、強い圧力を加えたローラーもしくはベルトの対の間を通すことで、トナーが溶かされ、紙に圧着します。
不具合と原因
画像不良の不具合は、この工程のいずれかで問題が生じることで発生します。
用紙の進行方向にスジが入っている場合は搬送経路上のどこかに異物が詰まっていたりキズが発生していることが多いです。
また、現像や定着などのローラーに回転ムラがあると進行方向とは垂直に等間隔で線が表れる画像不良もあります。
このように、「印刷物に線が入る」場合は、線の方向で異なる原因が考えられます。また、転写や定着の工程では、圧力をかけながら回転しているローラーがあり、ローラーの前奥で圧力差が生じてしまうと、用紙が斜めに搬送されて、紙詰まりを起こしたり、シワになってしまう不具合が発生します。
注意点
画像不良が発生した場合は、どの工程に問題が生じているのか?を切り分けることが重要です。
そのため、むやみに本体を開けたりバラシたりせずに、メンテナンス業者に連絡しましょう。可能であれば出力された画像は取っておいて、どのようなモードで出力したか?などをメモしておくと原因究明がしやすくなります。
また、トナーの飛散は画像不良や機能不良にも繋がります。トナーを交換する際は、他の場所へ飛散させないように注意して行いましょう。
排紙
画像や文字が印刷された用紙は定着後の熱を冷ますため、ファンによって冷却され、静電気を除去する除電ブラシを通過して排紙トレイへ排出されます。
排出の向きを裏向きに指定していたり、両面コピーを行う場合などは、一度通過させた用紙をスイッチバックさせて、再び搬送経路へ戻す反転動作を行います。
不具合と原因
搬送と同様に、定着後の加熱された用紙を搬送するために、紙詰まりのリスクが高まります。
特に反転動作のスイッチバックを行う際、瞬時に搬送経路を切り替えるため、電気的な制御と機械的な動作が確実に連動している必要があります。
この工程で初期不良でない場合は、モーターなど電気的な不具合の方が多いでしょう。
注意点
搬送の工程と同様に、紙詰まりが発生した際には、どこでどのような状態になっているのか?を、しっかり確認したうえで処理を行います。
基本的には、紙詰まりを処理する時に開く扉側の方に機能を持たせていることが多いです。部品の位置ズレやモーターに繋がる配線に影響を与えないよう、扉の開け閉めは丁寧に行いましょう。
【全メーカー対応】複合機のお見積り
30社の複合機販売店を独自調査したコピー機Gメンが、安さと対応力に優れた販売店を2~3社ご紹介します。
* * *
まとめ
コピー機・複合機は、簡単に画像や文字を複写しているように見えて、内部では、かなり精密な動作が高速で繰り返し行われています。
構造や動作についての理解が少しでもあると、不具合にも慌てずに対応できるようになります。また、メンテナンス業者に修理を依頼する場合も、具体的に話すことができるため、迅速な解決に繋がるでしょう。
簡単に買い換えられる安い製品ではないので、少しでも構造を知り、正常な状態で長く使えるようにすることが大切です。
- 故障のリスクを減らすため、長く使用していくために、印刷の仕組みを理解することは重要
- オフィスで使用されるコピー機は「電子写真方式」といい、静電気でトナーを紙に転写する技術
- 給紙してから、印刷された用紙を排出されるまで多くの工程を経ており、不具合の原因は様々
- 不具合が起きたときは慌てずに、どこでどのようなことが起きているのか理解すること
* * *