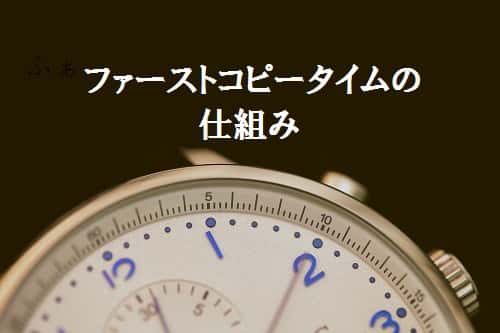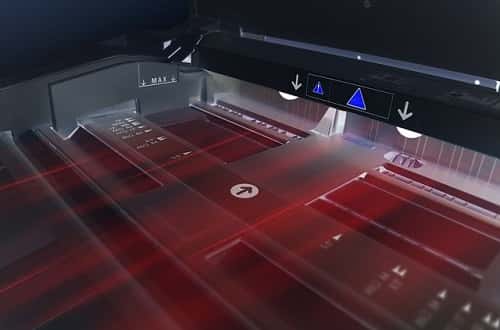【全メーカー対応】複合機のお見積り
30社の複合機販売店を独自調査したコピー機Gメンが、安さと対応力に優れた販売店を2~3社ご紹介します。
* * *
コピー機・複合機のドラムとは?

出典:ASKUL
コピー機・複合機には『ドラム』と呼ばれる重要な部品があります。
聞いたことはあってもドラムがどのような役割を果たしているのか?までは知らない方が多いでしょう。そこで今回は、コピー機・複合機の構造や工程を知るうえで欠かせない『ドラム』についてお伝えします。
大手事務機メーカーのコピー機部門で、生産技術職として約8年勤務していました。生産中の不具合対応や故障で返品された本体のチェックなど、ほぼ毎日コピー機をバラしており、コピー機・複合機の内部構造や印刷の仕組みについて熟知しています。
コピー機の内部構造の理解やドラムのメンテナンス方法などに是非お役立てください!
コピー機・複合機のドラムと印刷の仕組み
コピー機・複合機のドラムを正式には『感光体ドラム』と言います。
特殊な材料が何層にもコーティングされた大きな筒状の形をしており、基本的には、この筒状の部品単体を『ドラム』と言います。ただし、一般的には周辺のクリーニング部品やプラスチック容器なども含め、交換部品として1つのユニットになった『ドラムカートリッジ』のことを分かりやすく『ドラム』と呼んでいます。
『ドラム』=筒状の部品単体
『ドラムカートリッジ』=クリーニング部品やプラスチック容器も含めたユニット=これを通称ドラムとも言う
『ドラム』の役割を知るためには、印刷の仕組みから理解していきましょう。
そもそも、コピー機・複合機は、どのように画像や文字を印刷しているのでしょうか?
コピー機・複合機の印刷技術は「電子写真方式」と呼ばれ、顔料で着色された粉状の樹脂であるトナーを静電気の力で紙に転写して画像や文字を描きます。この際、画像や文字の通りに用紙へトナーを運んでくれる役割を果たしているのがドラムです。
ちなみに、主に家庭などで使用されるプリンターは「インクジェット方式」と呼ばれ、紙に直接インクを吹き付けることで画像や文字を描いています。
【全メーカー対応】複合機のお見積り
30社の複合機販売店を独自調査したコピー機Gメンが、安さと対応力に優れた販売店を2~3社ご紹介します。
* * *
コピー機・複合機の印刷工程
コピー機・複合機の印刷方式である「電子写真方式」では、画像や文字が印刷されるまでに、以下の工程を経ています。
- 帯電 → ドラム表面全体を均一に帯電させる
- 露光 → 出力された画像や文字の通りに光を当て、ドラム表面内に電荷の差を発生させる
- 現像 → 電荷の差によって、光が当たった部分にのみトナーが吸い寄せられドラムに像が描かれる
- 転写 → トナーによって描かれた像を紙へ直接転写する、または転写ベルトに1度移してから紙へ転写する
- 定着 → 紙に乗せられたトナーに熱と圧力を加えて定着させる
これらの工程からも分かる通り、ドラムは①帯電~④転写までの大部分を担っており、印刷品質に関わる重要な役割を果たしています。
コピー機・複合機のドラムカートリッジとは?
ここからは、交換部品としての『ドラム』=『ドラムカートリッジ』について説明していきます。
基本的に、モノクロ機には1つ、カラー機には各色分の4つのドラムが搭載されています。カラーの場合、4つあるのは「タンデム方式」と言って、各色で工程を分けるためで、ドラム単品自体は同じものを4本使用しています。
カラー機でもドラム1本で4色分を賄う「ロータリー方式」のタイプもあります。
これは、画質や色の再現性に優れていますが、印刷速度が遅くなってしまうため、一般のオフィスで使用されている機器は、ほとんどが「タンデム式」です。
このドラムを抱えたユニットのことを『ドラムカートリッジ』と呼び、消耗品であるドラムを簡単に交換できるように独立したユニットとなっています。
また、モノクロ機の古い機種の中には、ドラムカートリッジとしてユニット交換できる仕組みになっておらず、ドラム単品のみ交換する仕様の機器もあります。
そのような製品では、ドラムを抱える部分を『ドラムユニット』と呼んでいましたが、現在は『ドラムカートリッジ』と『ドラムユニット』を同義と捉えて良いでしょう。
ドラムカートリッジは、帯電させるためのゴムローラーや、転写しきれなかったトナーを清掃するためのクリーニングブレードなどが一体となっているユニットです。
ドラム交換では基本的に、このユニットごと取り換えることになります。
それとは別に、トナーを供給するための『トナーカートリッジ』と呼ばれるユニットもありますが、ドラムカートリッジとトナーカートリッジが一体となって、交換パーツ設定されている製品もあります。
【全メーカー対応】複合機のお見積り
30社の複合機販売店を独自調査したコピー機Gメンが、安さと対応力に優れた販売店を2~3社ご紹介します。
* * *
ドラムの寿命・交換するタイミング
ドラムは消耗品であり、交換の目安としてトナーを3回替えるタイミングです。
印刷枚数で言うとA4用紙で10,000~12,000枚くらいで、寿命が近付くと、コピー機・複合機がカウントしている印刷枚数などを目安に、交換を促すメッセージを出してくれます。
ドラムは寿命になっても、すぐに印刷できなくなってしまうものではありません。ただし、画像不良を起こす可能性が高くなるので、定期的に交換するようにしましょう。
ドラムの清掃・メンテナンス
製品によっては「ドラムクリーニング」のモードを備えています。
このモードがあると、画像にムラのようなものが出た時に有効です。たとえば、フロントドアを長時間開放していると、ドラムが光で疲弊し、転写不良を起こしてしまうことがあります。この時に、クリーニングでドラムをリフレッシュすることができます。
それ以外の画像不良は、クリーニングだけで解決しないことが大半です。
画像不良が起きた時、ドラムカートリッジに原因があれば交換することで解決できるケースもあります。しかし、ドラムだけでなく、トナーカートリッジや転写&定着エリアなど、他の原因も考えられる場合は切り分けが必要です。
ユニット交換を行う前に、一度メンテナンス業者などに連絡をして見てもらった方が良いでしょう。
また、交換だけなら、業者に頼まなくても可能です。
その場合、ドラムが露出した状態で本体の外へ長時間放置しないように気を付けて下さい。ドラム表面にキズをつけてしまったり、蛍光灯の光で焼き付けのような状態になると、正常に機能を果たせなくなってしまいます。
まとめ:ドラムはコピー機・複合機の心臓である!
『ドラム』について、その役割と重要さを理解して頂けたでしょうか?
印刷にあたってドラムは、心臓のように大事な部品です。状態と寿命をしっかり把握して使いましょう。
- ドラムは筒状の部品のことを指し、正式な名称は「感光体ドラム」
- 一般的には「ドラムカートリッジ」を「ドラム」と呼ぶ
- 印刷の工程で重要な役割を担い、印刷品質への影響が大きい
- 消耗品のため、交換しやすいように「ドラムカートリッジ」としてユニットになっている
- 寿命の目安はトナーを3回交換するタイミング
- もしくはA4用紙で10,000枚~12,000枚の印刷枚数
- 取り扱いが難しいので不具合が起きたら業者へ連絡。交換の際は丁寧に行う!
* * *